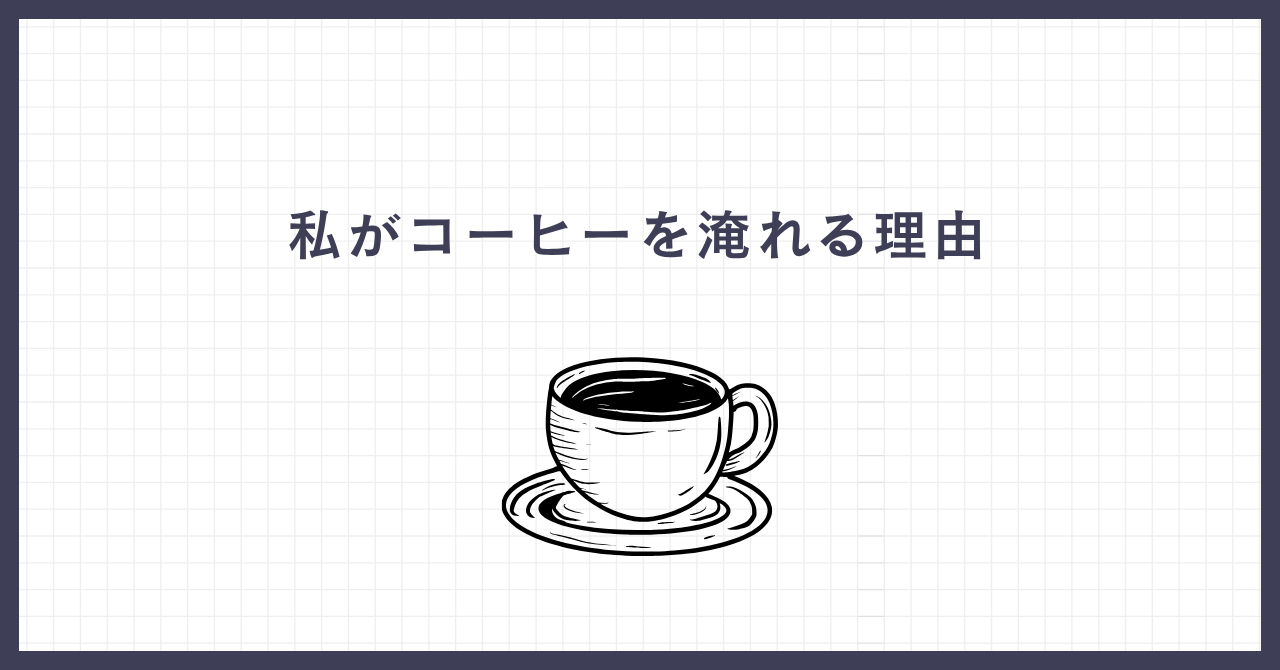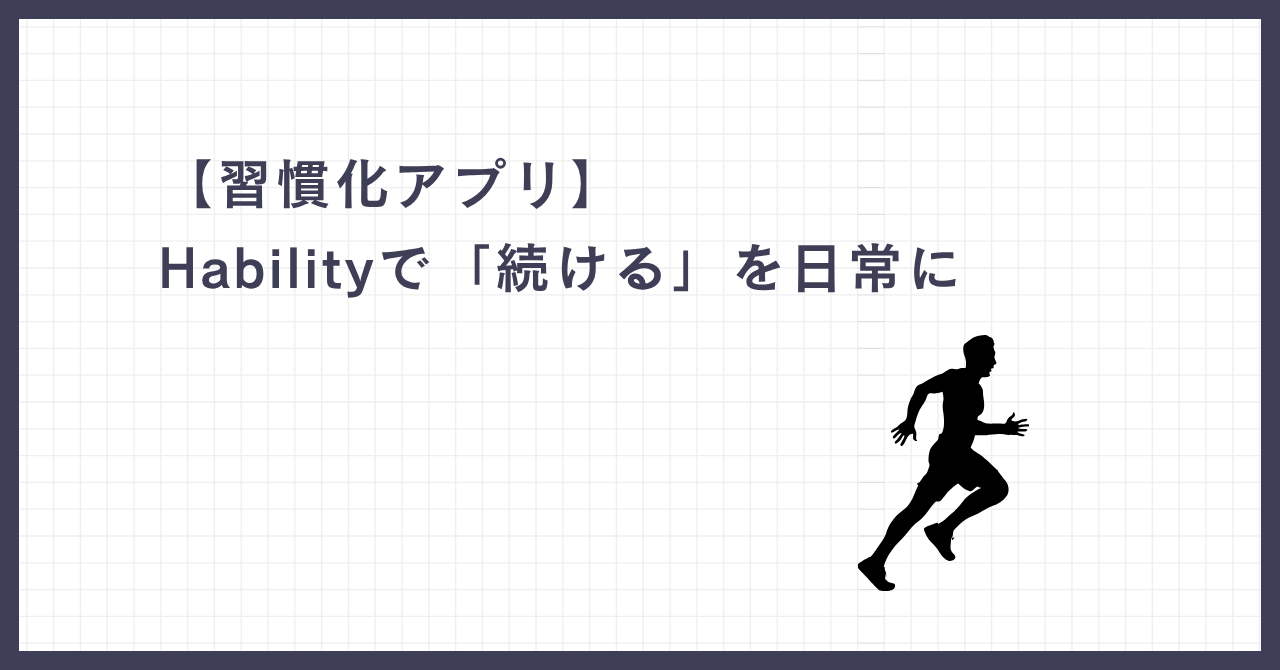ふと、私はなぜ、毎朝コーヒーを自分で淹れているのかについて考えてみた。実を言うと、大学2年生からハンドドリップを続けてきた。
単にコーヒーが好きだからではないかと考えたが、それだけではない気がする。単にコーヒーを飲みたいだけであれば、コーヒーマシンに任せればいい。ボタンひとつで、一定の品質の一杯が手に入る。けれど、私はそれを選ばない。
朝の数分を使って、豆を計り、挽き、お湯を沸かす。抽出のあいだ、ただ静かにその時間を過ごす。忙しい朝にこの手間を残しているのは、そこに何か意味があるからだと思う。
お湯を注ぐと、粉がふくらみ、香りが立ちのぼる。その瞬間に、空気が少しだけ変わる。コーヒーを淹れることは、味を作る行為であると同時に、空間を整える行為ではないかと考えてみた。部屋の空気をゆっくりと温め、自分の心拍を落ち着かせていく。
私が考えるハンドドリップの魅力は、味の再現性の低さにある。同じ豆でも、湯の温度や注ぐ速さでまったく違う味になる。正確ではない。少しの違いが、自分の状態をそのまま映してくれるような感覚がある。昨日の焦りが残っていれば苦く、心が穏やかなら甘い。そういう曖昧な関係性の中に、私の時間があるのではないかと考えた。
完璧に再現できない一杯を毎日淹れるというのは、ある種の諦めでもある。効率や最適化を求める現代の流れに逆らうように、あえて不確かさを受け入れる行為だ。私はどうしても、この“不確かさ”に惹かれてしまう。なぜだろう。おそらく、そこには「揺らぎ」があるからだ。生きているということは、予定通りにいかないことを含めて受け入れることだと思う。コーヒーの味も、人生の一部のように日々変わっていく。それを確かめることが、私にとっての朝の儀式なのかもしれない。
効率の良さや正確さを重んじる社会では、“同じ結果を出せること”が優秀さの証とされる。だがコーヒーを淹れるときの私は、それとは真逆にいる。毎日同じようにしようとしても、同じにならない。気温、湿度、豆の状態、心の揺れ――すべてが味に影響する。つまり、そこには自分が否応なく現れてしまう。逃げ場のない、正直な行為。私はそれを通して、「今日の自分」を確かめているような気がする。
お湯を注ぐあいだは、言葉がいらない。何かを考えているようで、実は何も考えていない。ただ、香りを感じ、音を聞き、手の感覚に集中する。五感がすこしずつ目を覚ましていく。その沈黙の中で、私は自分の思考がほどけていくのを感じる。焦りや緊張のようなものが、少しずつお湯に溶けていく。コーヒーを淹れることは、整える行為というよりも、むしろ自分をいったん“ほどく”ための行為だと思う。思考を組み立てる前に、一度それを解いておく。そうしないと、私の日々はすぐに硬くなってしまう。
コーヒーを淹れる理由を問うことは、もしかすると「なぜ人は手間をかけるのか」という問いと同じだ。合理的に考えれば、手間など省いた方がいいに決まっている。だが、手間を省くたびに何かが削れていく気がする。そこにあった“余白”や“体温”のようなものが消えていく。私はその消えゆくものを確かめるように、今日もドリップをしているのかもしれない。
人間らしさというのは、たぶん“無駄”の中にある。効率や便利さの先には、もう人間が介在しない世界が広がっている。だからこそ私は、この小さな非効率を守りたい。誰にも邪魔されない数分間、自分の手で時間を作ること。その時間があるだけで、一日の始まりがまるで違う。
私はきっと、正確な味を求めているのではない。ただ、静かに考えるための余白を求めているのだ。今日もまた、お湯を注ぐ音に合わせて、思考がゆっくりと立ちのぼっていく。香りが部屋を満たすころには、少しだけ呼吸が整い、ようやく一日が始まる。